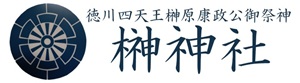榊神社とは
榊神社とは

廃藩置県が行われた明治4年(1871年)、旧榊原家高田藩有志が「報本反始」の理念を掲げて藩祖康政公を祀る神社設立を発議、広く旧藩士・領民の協賛を得て、「榊神社」を社名に同9年(1876年)対面所(現在地)跡に社殿・社務所を建立、康政公着装の鎧・冑・刀剣類等を神器に奉戴して創建、以後、3代・忠次公 11代・政令公 14代・政敬公を合祀するとともに、神楽殿・雙輪館を造営、現在に至る。
【御祭神】
藩祖・榊原康政公
15歳より徳川家康公に伺候以来、誠忠比類なく、剛勇・智謀兼備にして数々お武功を挙げるとともに無私・公正にして敵味方の別なき信望を集め、徳川政権樹立に貢献、「徳川四天王」と称される。立藩の地、館林にありては、城下整備、民生安定に優れた事績を残すとともに、「尚武勧学」の気風醸成に努め、その遺風は榊原家藩風として転封の地、白河・姫路・村上・高田へと受け継がる。

3代・榊原忠次公
襲封の地要衝白河・姫路においては武備怠らざる一方、広く古今和漢書収集・著名学者招聘など学問・文芸振興に努め、「文治時代」を先導するとともに「愛民」の志に基づく民福優先の徳行と清廉にして温和な人柄とが相俟ってあまねく領民の敬慕を集む。また、幕閣中枢「執政」に任ぜられるや、殉死禁止など「武家諸法度」改正ほか旧弊克服に業績を積む。

11代・榊原政令公
高田転封後、貢租不足の上、相次ぐ自然災害によって極端にひっ迫したした財政再建のため、藩士給禄借り上げ・諸産物に対する新規課税・領民からの借金など非常手段をとらざるを得なかった9代・10代藩主時代の路線を継承、さらに「藩士内職許可」など「体面にとらわれない緊縮策」を推進する一方、山間高冷地開拓・赤倉温泉開湯など殖産興業にも意を用い、財政立て直しの曙光を見るに至る。
14代・榊原政敬公
長州戦争に再度出兵、戊辰戦争勃発後の急変した政局に処して藩論を「哀訴諌諍」に集約、折衝するも、新政府による「不審藩」の疑念払拭容易ならざる上、東征軍先鋒に任ぜられて各地に転戦、さらには戦後、会津降伏人多数を預けられるなどの苦難を克服する。廃藩置県後、城址売却の巨費を旧藩士子弟育英基金に下賜されるなどの事績を刻む。